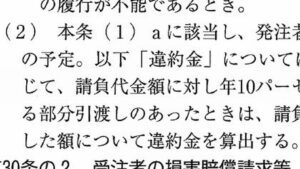擁壁崩壊の法的責任は誰が負うのか? 杉並区住宅倒壊事例から学ぶリスクと対応
2025年9月30日夜、東京都杉並区、方南町駅の近くの住宅地で木造2階建の住宅が擁壁側へ傾き、最終的に全壊するという事故がありました。
幸い人的被害は報じられていませんが、がれきの一部は道路を挟んだ隣地のマンション敷地に達し、近隣には自主避難が呼びかけられています。現場の擁壁にはひびやふくらみがあったとの住民証言があり、区と警察が原因を調査中とのことです(TBS NEWS DIG(2025年10月1日)) 。
また、杉並区によれば、当該敷地の所有者に対しては、区建築課から擁壁の補強工事等改善をするようにと指導をしていたとのことです(杉並区 堀ノ内一丁目の家屋倒壊について(2025年10月1日))。
本記事では、この事故のように、擁壁が崩壊するなどして隣地などに損害を与えた場合の法的責任について解説します。
土地工作物責任(民法717条)について
擁壁が崩落し第三者に損害を与えた場合、まず適用が検討されるのが「土地工作物責任」です。
民法717条によれば、土地の工作物(建物や擁壁など土地に設置した物件)の、設置または保存に瑕疵(欠陥)があることによって損害が生じた場合には、その占有者または所有者が責任を負うとされています。
民法717条1項:
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
賃借人や管理者など、土地の占有者に過失がある場合は占有者の責任となります。一方、占有者に過失がない場合は所有者の責任となります。所有者は過失がなくとも責任を免れません(無過失責任)。
また、前の所有者が工事をしたものであっても、基本的には事故時の所有者が責任を負います。知らなかったという反論は通りませんので、土地の購入時には擁壁に関する調査をしっかり行うべきです。
※土地工作物責任については過去記事(がけ崩れ(斜面崩落)の責任は誰が負う? 土地所有者が負う法的リスクについて)もご参照ください。
損害賠償責任の範囲
上記の土地工作物責任が成立する場合、所有者などが負う損害賠償責任は場合によって重いものとなります。
擁壁が崩落するような事態となれば、隣地側の建物への被害は深刻なものとなり得ます。場合によっては建替えが必要となり、その場合には数千万円単位の賠償額となります。
また、道路側に崩落して通行人を死傷させてしまった場合にも被害は深刻です。2020年の神奈川県逗子市でのマンション敷地の崩落事故では、巻き添えで亡くなった通行人の遺族に対し、所有者側は1億円を支払う内容の和解が成立しています。
なお、加入している保険(施設賠償責任保険など)によってはこれらの損害賠償金が保険でカバーされる場合があります。
刑事責任
上記の損害賠償はあくまで民事上の話ですが、擁壁の必要な管理を怠ったため事故が起こり人(通行人など)を死傷させてしまった場合には、(業務上)過失致死傷罪が成立する可能性もあります。
実際に、死亡事故のケースで刑事告訴された例もあります。
行政側の責任は?
建物や擁壁などが危険な状態にある場合、行政はどのような措置をとることができるのでしょうか。
行政側の監督手段
建物や擁壁などは、「建築基準法」や「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)のほか、当該建物が空き家であれば「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空き家法)の規制対象になります。
危険性が高いなど法定の条件を満たした場合に、自治体が所有者などに対して、法定の手続を経たうえで修繕などの措置をとるよう命令することができるとされています。
命令に従わない場合には行政代執行法に基づく行政代執行が行われます。自治体が強制的に工事を行い、その費用を所有者などから徴収します。
なお、盛土規制法や空き家法では、緊急の場合には命令の手続を飛ばして即時に代執行を行うことも可能です(緊急代執行)。
監督手段の現実性
もっとも、法的には可能であるといっても現実には代執行まで進む例は少ないです。
自治体としても、なるべく強制手段ではなくその前段階での指導や勧告により、所有者に自主的に対応してもらおうとすることが多いですし、そもそも件数が多すぎて全ての物件に対応しきれないというのが現実です。
また、代執行となれば一時的には自治体が費用を負担しなければならないことに加え、所有者の財産状況によってはそれが徴収不能となり、自治体の持ち出しになってしまいます(都市部の土地であれば費用の徴収は可能ですが)。
こうした事情から、自治体による監督も限界があるのが現状です。
監督責任
したがって、事故が起きた場合に行政の監督責任を法的に問うことはなかなか難しいと思われます。
隣地側による法的措置
では、建物や擁壁が危険な状態にある場合、その隣地側としては、行政に通報する以外に何らかの手段はとれないのでしょうか。
法的措置としては、隣地側は、相手側(危険な側の所有者)に対して、危険を防止する工事を求めることができます(妨害予防請求権)。相手側が任意の要求に応じない場合は、訴訟で請求することになります。
もっとも、訴訟手続は1年以上かかることもざらですので、危険が切迫している緊急の場合には間に合いません。このような場合には、裁判所に仮処分を申し立て、仮処分手続により工事を行わせることになります。
なお、いずれの場合で勝訴したとしても、相手側が判決に従わない場合には自らが費用を立て替えて工事をさせなければなりません(代替執行)。しかし、擁壁の工事費用は1千万円を超えることも珍しくありませんので、相手側が拒否している場合には難しいのが現状です。
所有者の責務
いずれにせよ、擁壁の問題は、万一事故が起きれば大きな被害が予想されます。前述のとおり所有者は過失がなくても損害賠償責任を免れませんし、危険性を知りながら放置していた場合には刑事責任を負いかねません。
所有者は擁壁を安全に保つ義務がありますので、膨らみや亀裂、排水状況などの点検はもちろん、場合によって業者に調査を依頼し、危険性が高ければ補修工事や造り替えを行う必要があります。
とはいえ、擁壁工事の費用は高額になることが多い(数百万円~1千万円超)ため、計画的な対策が必要といえます。また、近年は擁壁の安全対策工事に助成金を出している自治体も増えていますので、まずは専門業者や自治体に相談をしてみるのがよいかもしれません。