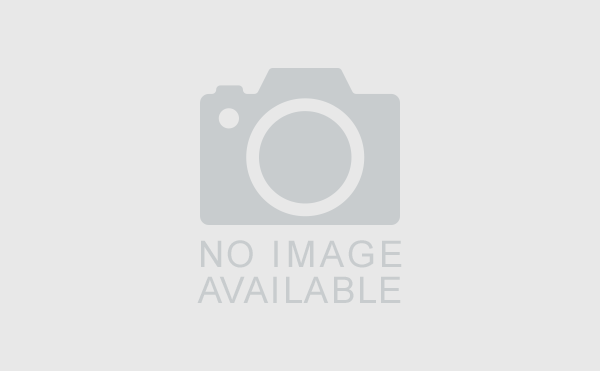老朽空き家の外階段崩落事故に学ぶ――不動産オーナーが負う管理責任とリスク対策

2025年7月13日夜、長崎市にある2階建て空き家アパートで外階段の踊り場が崩落し、高さ約4メートル下へ転落した所有者の男性が死亡し、不動産関係者の男性も負傷するという事故が起きました(階段踊り場が崩落、40代男性が死亡 長崎のアパート - 日本経済新聞(2025年7月15日))。
なお、当該アパートは既に居住者がいない空き家でしたが、過去にも「屋根材が飛散している」との苦情が長崎市に寄せられ、市は空家等対策特別措置法(空家法)に基づく指導を複数回行っていたようです。
今回はオーナー自身が被害者となってしまいましたが、老朽化建物の管理に関してオーナーはどのような責任を負うのでしょうか。
目次
空き家でも免れないオーナーの法的責任
民法717条「土地工作物責任」
土地や、土地上の工作物(建物など)に、設置または保存の瑕疵(通常有すべき安全性を欠いている状態)があり、これによって他人に損害を与えた場合、その占有者または所有者は損害賠償責任を負います。これを土地工作物責任(民法717条)といいます。
占有者は過失がある場合に限られますが、所有者は過失がなくても損害賠償責任を負うことになっています。この点で、土地工作物責任は所有者に非常に重い管理責任を課しているといえます。
したがって、建物が空き家であり誰も使っていなかったとしても、所有者は建物を所有している限りこの責任を免れることはありません。
老朽化した建物が倒壊したり、屋根や外壁の一部が剥がれ落ちたりして近隣住民や歩行者に被害を及ぼすことのないよう、常に安全な状態を維持する必要があります。
建築基準法による修繕・除却命令
建築物が劣化するなどして保安上危険な状態となった場合には、市町村長は建築基準法10条に基づき、所有者等に修繕や除却などの措置を勧告または命令することができます。
命令に従わない場合は行政代執行により強制的に解体されることになります。
空家法による勧告・命令と課税強化
空家法は、そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態になったと認められる場合に、市町村長は上記と同様、除却などの措置を勧告または命令することができます。
上記の建築基準法に基づく命令に比べて要件が明確に定められているため、除却を目的とする場合には空家法の命令の方が利用されやすいようです。
刑事責任
ここでは簡単に触れますが、他人に被害を及ぼすような状態であったことを認識しながら修繕など必要な措置をとらずに放置し続けた場合には、刑法上の(業務上)過失致死傷罪が成立する可能性もあります。
老朽化物件を保有する際に確認すべきポイント
定期的な管理・診断が必要
以上の法的責任からも明らかなように、オーナーには物件が被害を及ぼさないよう安全な状態に保つ責任があるといえます。
売却予定の空き家であっても、階段やバルコニー、屋根など外部構造部の安全性を専門業者に点検してもらいましょう。危険箇所が見つかった場合は、簡易補修でも先に実施することで事故リスクを抑えられます。
なお、施設賠償責任保険に加入できればよいのですが、管理不全の状態ですとそもそも加入が難しい場合があるので過度な期待はできません。
契約不適合責任が免責されない場合に注意
売却する場合、中古売買では契約不適合責任の免責特約を入れることがありますが、仮に免責特約を入れても、売主が知りながら売却した場合には責任を免れません(民法572条)。
解体・更地化と税負担の比較検討
倒壊リスクが高い場合は解体して更地で売却する選択肢も視野に入れましょう。
解体すると住宅用地特例が使えなくなり固定資産税が上がりますが、空家法に基づく管理不全空家の勧告を受けた場合にも同じく優遇措置が外れる点に留意が必要です。
いずれは解体する必要がありますし、万が一の場合の損害賠償責任の問題もありますから、老朽化が激しく修補が現実的でないような場合には、早い段階で解体を検討した方がよい場合もあります。
まとめ――「使わない不動産」は早めに対応の検討を
空き家は収益を生まないだけでなく、崩落や倒壊などによる加害リスクを内包しています。
冒頭の事故のケースは、行政指導後も有効な対策を講じなかった結果、所有者自身が命を落とし、重大な損害賠償リスクを残した事例ということもできます。
不動産オーナーとしては、法律上の維持管理義務を踏まえて、早期に現状を把握して、修繕あるいは解体・売却を検討すべきといえます。