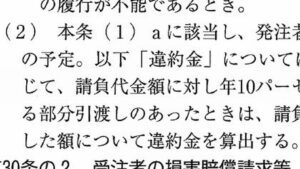豪雨による地下駐車場での浸水被害…自動車が水没した場合の駐車場管理者の責任は?

近年、記録的な集中豪雨や大型台風が日本各地で頻発し、家屋の床上浸水・床下浸水だけでなく、地下駐車場での浸水被害も深刻化しています。特に、地下駐車場は周囲より低い位置にあるため、一度浸水すると駐車中の車両が水没し、廃車になってしまうケースも少なくありません。
三重県では、9月12日の大雨で地下駐車場に浸水し274台の自動車が被害にあう事故が起こりました(雨で水没の地下駐車場、被害は274台 排水ほぼ完了 三重・四日市 [三重県]:朝日新聞(2025年9月16日))
このような浸水被害が発生した場合、駐車場の管理者は車の所有者に対して損害賠償責任を負うのでしょうか。
本記事では、この問題について、裁判例から管理者の責任がどのように判断されるのか、そしてどのような対策が求められるのかを解説します。
目次
管理者の損害賠償責任の法的根拠
駐車場といっても、単体の駐車場もあれば、店舗やオフィスビル、マンションに併設するものもあります。
管理形態や利用者との関係によって、損害賠償責任を負う場合の法的根拠は債務不履行責任か不法行為責任に分かれます。もっとも、いずれの場合でも責任が認められるかどうかの考慮要素には大きな差はありません。
• 債務不履行責任(民法415条) :賃貸借契約や管理委託契約において、管理側が負うべき義務を怠った場合に発生します。利用者と管理者の間に契約関係があることが前提です。
• 不法行為責任(民法709条) :管理側が、浸水などの被害を予見できたにもかかわらず、その回避措置を怠った場合に発生します。
裁判例から見る地下駐車場浸水と管理者の責任
実際の裁判例では、管理者の責任の有無は、予見可能性、浸水対策の状況、契約内容、情報提供の有無、そして豪雨の異常性といった多角的な要素から判断されています。ここでは、特に損害賠償責任が認められやすいケースと認められにくいケースの傾向を概観します。
損害賠償責任が認められやすいケースの傾向
次のような事情がある場合に、管理者の責任が認められやすくなるといえます。
- 過去の浸水履歴と対策の不備:過去に駐車場で浸水被害が発生していたにもかかわらず、それに対する十分な対策を講じていなかった場合。
- 予見可能な範囲の降雨:当日の降雨が、過去の降雨記録や当日の予報などから予見可能であった場合。
- 契約上の緊急対応義務の不履行:管理契約等で緊急時の対応義務が明確に定められているにもかかわらず、それを怠った場合。ただし、免責規定の適用が争点となることもあります。
- その他、裁判例としては見当たりませんでしたが、駐車場の排水設備が通常備えているべき性能を満たしていなかったり、管理の不備により故障していたなどの場合は、管理者側の責任が認められやすくなります。
損害賠償責任が認められにくいケースの傾向
一方、次のような事情がある場合には管理者の責任が認められにくくなるといえます。
- 過去の浸水被害がない:過去の大雨の際にも浸水の被害がなかった場合。
- 極めて異常な豪雨(想定外の大雨):例えば1時間あたり100mmを超えるような、過去に例のない短時間集中的な局地的豪雨(ゲリラ豪雨)など、その発生を予見できなかったような想定外の大雨の場合。
- 緊急時の回避措置の困難性:猛烈な雨の中で緊急的に止水板を設置するなどの回避措置が、設置者の生命・身体に危険を及ぼす可能性があり、社会通念上義務を負わせるのは酷に過ぎると判断されるような場合。
- 契約上の免責規定の適用:管理契約に免責規定が設けられており、豪雨による同時多発的な緊急事態や道路事情の悪化により、警備員等が通常の時間内に現場に到着できなかったような場合。
(参照)横浜地判H24.7.17 東京地判H25.2.28 名古屋高判H28.6.24 東京地判H28.9.12 東京地判R2.3.26 東京地判R2.11.6 東京地判R4.3.11 東京地判R4.9.1
管理者としての対策ポイント
これらの裁判例の傾向からすると、管理者側としては次の観点から対策しておく必要があるといえます。
設備のメンテナンス・運用の見直し
これは当然のことですが、通常想定される程度の雨が降っても本来の性能どおり排水できるか、メンテナンスや確認を行うことは大前提です。
また、大雨が予想される場合の運用として、早期に閉鎖して止水板等の対策をする(独立した駐車場の場合)、早期に閉鎖して駐車場の使用を禁止する(店舗等の場合)、事前に車を地上に出して避難させるようルールを設定して周知する(マンションのピット式駐車場等の場合)といった対策が必要になるでしょう。
管理委託契約の見直し
駐車場の管理を受託している管理会社の場合は、改めて、契約上「どのような場合にどのような義務が生じるか」「どのような場合に損害賠償責任を負うか」が定められているかを確認する必要があります。
緊急時の巡回・出動義務などが具体的に定められている契約では、それに違反した場合に責任が認められやすくなります。急な大雨が多発する近年において、契約で定められた措置を行うことが現実的でなくなっているような場合には、契約内容の見直しを検討すべきです。
一定の場合には責任を負わないという「免責条項」も重要です。ただし、実際の裁判例では必ずしも免責条項の規定だけで結論が決まっているわけではありませんので、過信は禁物です。
事前の説明(賃貸の場合)
以上のほか、マンションにおける駐車場や月極駐車場など、賃貸借契約により継続的に利用する駐車場の場合には、事前に利用者に上記のリスクを十分に説明しておくことが必要です。
特に、過去に浸水被害があったのであれば(たとえ被害が不可抗力であったとしても)その事実は事前に利用者に説明しておくのが望ましいです。
まとめ
地下駐車場での浸水被害を巡る管理者の責任は、その事前の予見可能性、講じられた対策の適切性、契約上の義務の範囲、そして当日の降雨の異常性など、多岐にわたる要素から総合的に判断されます。
管理者はもちろん、利用者も自らのリスクを認識し、適切な情報収集と対策を講じることで、豪雨災害による被害を最小限に抑えることが可能です。