みなし労働時間制とは
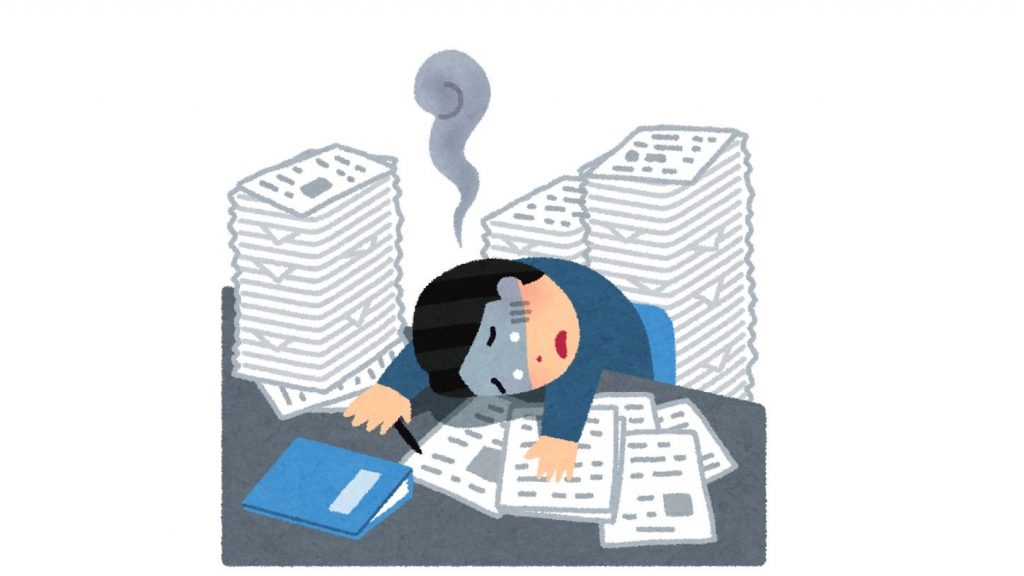
最近は、何かと過労死の問題がニュースになりがちです。
先日発表されたこちらのニュース
NHK女性記者に労災認定 過労死、残業159時間(日経新聞・2017年10月4日)
NHKの説明「事実ではない」 過労死記者の遺族が会見(朝日新聞・2017年10月13日)
にもありますが、亡くなったのは2013年で、翌2014年に労働基準監督署から労災認定を受けていたそうです。
一月あたりの残業時間が最大159時間となっていたわけですから、心身に不調をきたすのは当然といえます。
このような事態を防ぐため、会社は、従業員の労働時間を適切に管理して過重労働を防止する義務を負っています。
しかし、今回の件ではNHKが佐戸さんの過重労働を把握しきれていなかったようですね。
過重労働を把握しきれなかったことの一つの原因として、佐戸さんに「みなし労働時間制」が適用されていたことが挙げられています。
みなし労働時間制に対しては「長時間労働を促進させる」などの批判もあり、耳にしたことのある方も多いのではないでしょうか。
しかし、実際には「どれだけ働かせても残業代を払わなくてよい制度だ」という誤解も多くあることから、この制度について正確に理解している方は多くないのではないかと思います。
そこで今回は、「みなし労働時間制」について概説します。
「みなし労働時間制」とは
みなし労働時間制とは、実際の労働時間にかかわらず特定の時間労働したものとみなす制度をいいます。
例えば、労働時間をあらかじめ1日8時間と定めておけば、実際に働いたのが5時間であっても10時間であっても「8時間働いた」とみなされます。
一般的な労働形態は、会社の中や特定の現場において、命じられた作業を行うというものです。
そのため、従業員の出勤・退勤の時刻を管理することで、労働時間を管理することができます。
しかし、職種によっては労働時間のこのような管理方法が適切でない場合もあります。
例えば、
① ずっと外出しているためそもそも労働時間の把握が難しい場合
② 業務の性質上、会社が労働時間を管理するよりも、自身に裁量を持たせて管理させる方が適切である場合
には、一般的な方法で会社が労働時間を管理することはできないか、あるいは望ましくありません。
そこで、このようなニーズに対応するため、労働基準法では一定の条件のもとで「みなし労働時間制」を認めています。
具体的には、上記①に対応するのが「事業場外みなし労働時間制」、②に対応するのが「裁量労働制」です。
もっともこれらの制度は、悪用すればそれこそ「どれだけ働かせても残業代を払わなくてよい制度」になってしまいかねませんので、安易にみなし労働時間制を採用することはできません。
労働基準法では、厳しい条件の下で例外的に認められる制度なのです。
それでは、どのような条件でそれぞれの制度が認められるのかをみていきましょう。
事業場外みなし労働時間制
外勤の営業職や、旅行会社の添乗員など、ずっと会社の外で業務を行っているため会社が労働時間を把握することが困難な場合には、以下の規定により、一定の時間働いたものとみなすことができます。
労働基準法第38条の2 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
これを「事業場外(じぎょうじょうがい)みなし労働時間制」といいます。なお、冒頭の佐戸さんにもこの制度が適用されていたようです。
みなされる労働時間によって、この制度はさらに二つに分かれます。
一つ目は、
① 労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事すること
② 労働時間を算定し難いこと
という条件を満たす場合に、所定労働時間(就業規則に定められた通常の労働時間)労働したものとみなす、という制度です。
二つ目は、上記①②に加え、
③ 当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる
という条件を満たす場合に、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす、という制度です。
一定の残業を前提としている場合に採用されています。
通常は、就業規則のほか労使協定によってこの時間を設定します。
なお、当然ながら時間外手当や休日・深夜手当は発生します。
上記いずれの場合でも、結局、会社としては一定の時間分の給与を支払えば問題ありません。
そうすると、一見会社にとっては有利な制度にも思えますが、この制度を適用するための前提である、①の「労働時間を算定しがたいこと」という条件が、ハードルが高くなっています。
実際に裁判で争われた例では、会社がみなし労働時間制を採用していたと主張しても、具体的な業務遂行の手順やスケジュール指定があった場合には、会社の主張が否定されることがよくあります。
具体的には、行先やスケジュールなどについて会社から事前に具体的な指示がなされている場合や、従業員に詳細な行動内容の報告を義務付けている場合、従業員に携帯電話を持たせたうえで、常に会社に報告を求めたり会社から指示を受ける状態にさせていた場合などでは、「労働時間を算定しがたい」とはいえないため、この制度の適用が否定されています。
みなし労働時間制の適用が否定されれば、原則に戻って、実労働時間を基準とした給与・手当を支払わなければなりません。
このように、外勤だからといって安易にみなし労働時間制を採用しようとしても、後で裁判で否定されることがあります。
導入に当たっては、条件を満たすかどうかをしっかり検討する必要があります。
裁量労働制
従業員の業務によっては、会社が従業員に「ここで●時~●時まで働くように」と指示をして労働時間を管理するのが、適切でない場合があります。
そのような職種の場合に、労働時間の管理を従業員の裁量に任せられるようにするため、裁量労働制が認められました。
これにより、業務の遂行にあたり手段や方法、時間配分などを従業員自らが決定することが可能になります。
裁量労働制はさらに、①専門業務型裁量労働制と、②企画業務型裁量労働制に分かれます。
1.専門業務型裁量労働制
開発・研究に関する業務、クリエイティブな業務、その他専門性の高い業務に従事する従業員に適用されます。
法令で19種類の業種に限定されており(詳細はこちら)簡略化すると以下のとおりです。
1. 新商品・新技術等の研究開発
2. 情報処理システムの分析・設計
3. 新聞・出版・テレビ番組等の取材・編集
4. 衣服・製品・広告等のデザイナー
5. テレビ番組・映画等のプロデューサー・ディレクター
6. 広告等のコピーライター
7. システムコンサルタント
8. インテリアコーディネーター
9. ゲームソフトの創作
10. 証券アナリスト
11. 金融商品の開発
12. 大学の教授・准教授・講師(研究を主とする場合)
13. 公認会計士
14. 弁護士
15. 建築士
16. 不動産鑑定士
17. 弁理士
18. 税理士
19. 中小企業診断士
上記の類型に当てはまらない業種では適用できません。
(なお、各種の士業が挙げられている一方で、医師は対象外です(12にあたる場合を除く))
上記の業務についてこの制度を導入する場合は、就業規則にその旨を定めることはもちろんですが、そのほかに労使協定において、みなされる労働時間や、従業員が裁量を有すること、会社が講ずる健康確保措置や苦情処理措置を定めることが必要になります。
なお、冒頭に挙げたNHKの事例ですが、NHKでは2017年4月から記者を対象にした専門業務型裁量労働制を導入したそうです(発表資料)。
2.企画業務型裁量労働制
こちらは、事業運営上の重要な決定が行われる企業の本社などにおける、企画・立案・調査・分析などの業務が対象となります。
具体的には、会社の営業戦略や生産計画の策定、人事制度の制定など、会社全体の戦略に関する意思決定にかかわる業務が対象となります。
一見するとホワイトカラーの多くが対象になりそうですがそうではなく、会社の具体的な指示を受けることなく実質的にこれらの意思決定にかかわる役職・業務のみが対象となります。
導入のためには、労使委員会を設置し(単なる労使協定ではダメです)委員会において、みなされる労働時間や、従業員が裁量を有すること、会社が講ずる健康確保措置や苦情処理措置を定めることのほか、対象従業員の個別の同意を得ることなどを定める必要があります。
実務で注意すべき点
以上のうち裁量労働制については、大企業などごく一部の会社で導入されているにとどまり、中小企業において採用されている事例はほとんどありません。
他方、事業場外みなし労働時間制は中小企業でも目にしますが、特に中小企業が導入する場合には、適用が認められるための条件を満たしているのかについて注意が必要です。
人件費削減のために安易に導入・適用してしまうと、従業員の過労や、思わぬ残業代請求を招く結果になりますので、専門家と慎重に検討してください。

