入居者が逮捕された! 契約解除や残置物処分はどうするか
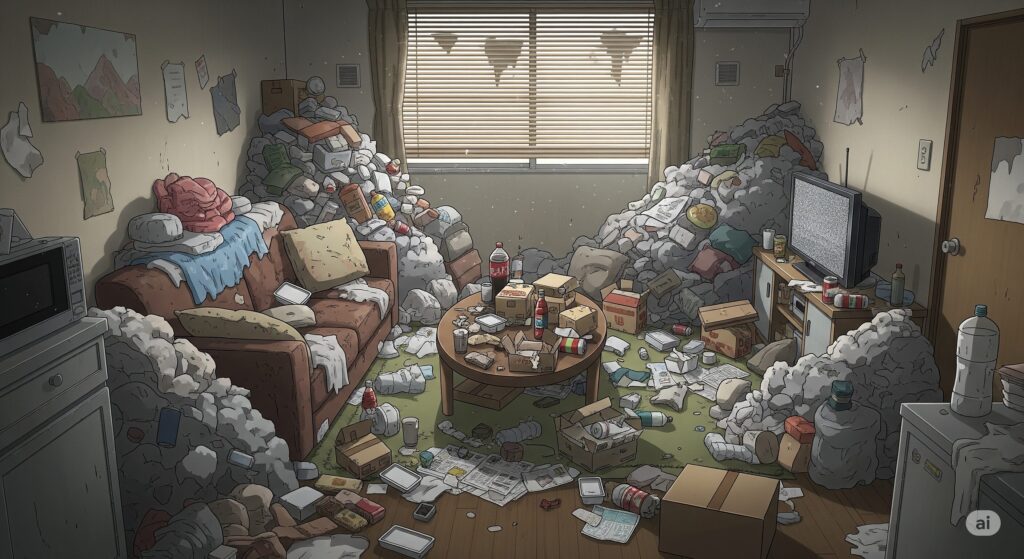
賃貸経営をしていると、入居者が突然逮捕されるという予想外の事態に遭遇することがあります。報道で知る場合もあれば、警察の家宅捜索で発覚したり、弁護士や家族から連絡が入ったりするケースもあります。
このような状況でオーナーや管理会社が慌てずに適切な対応を取るためには、初動対応・契約手続・残置物対策の3つの観点からポイントを理解しておくことが重要です。
目次
逮捕を知ったらまず何をすべきか
まずは事実確認
まずは事実関係を確認しましょう。
逮捕・勾留された入居者に弁護人(弁護士)がついていれば、弁護人に確認するのが確実です。弁護人と連絡が取れる場合は、どこの警察署に留置されているのかや、留置期間の見込み、本人の意思(賃貸借契約をどうするつもりなのか)などを確認しましょう。
弁護人がいない(連絡が付かない)場合でも、同居家族からこれらの情報が確認できる場合もあります。少なくとも留置先の警察署は確認しておきましょう。
本人への面会
弁護人や家族を通じて賃貸借契約の話ができればよいですが、それが難しい場合には、場合によってオーナーや管理会社担当者が、警察署や拘置所に面会に行くことになります。
その上で、本人と話をしたり書類のやり取りを行ったりします。書類のやり取りは郵送でも可能です(ただし、「接見禁止」となっている場合はやり取りができませんので事前に確認しましょう)。
逮捕されても契約は自動的に終了しない
入居者の逮捕等されてもそれ自体は契約終了事由に当たりませんから、入居者が逮捕等されても賃貸借契約は自動的には終了しません。
また、債務不履行というわけではないので、逮捕等されたというだけでは契約を解除することもできません。
契約を終了させる場合は合意で解約するか、別の債務不履行事由によって解除する必要があります。
契約を終了させる2つの方法
合意による解約
最もスムーズなのは、入居者本人に退去届を書いてもらう方法です。弁護士や家族を通じて書いてもらえる場合もありますが、特に家族を通じての場合は、本人が書いたのものかどうかの確認はしっかり行いましょう。
また、あわせて残置物処分の同意書も必ず書いてもらいましょう(後述)。
債務不履行解除
合意が得られない、あるいは連絡が取れない場合は、債務不履行により契約を解除することになります。
身柄の拘束が続けば多くの場合は賃料不払いとなります。不払いが3か月程度続けば債務不履行による解除が認められやすくなりますので、この段階で解除手続に進むことになります。
支払いの催告および契約解除する旨の通知(内容証明郵便を使うことが多い)を行います。宛先は、留置場(警察署)あるいは拘置所です。
残置物は勝手に処分してはいけない
「自力救済」は違法行為
なお、契約が終了しても、室内に残された家具や物品をオーナー側が無断で廃棄することはできません。
無断で廃棄してしまうと、違法な自力救済として器物損壊罪などに当たる可能性があり、また民事上も不法行為として損害賠償義務を負うことがあります。
残置物処分の同意書を取ろう
残置物を適法に処分するには、その旨の同意書を取っておけば確実です。
前述の合意解約の際に残置物処分の同意書を取得していれば、所有権放棄の同意に基づいて適法に処分できます。そのため、この同意書は必ず取るようにしましょう。
どうしても同意書が取れない場合は、ひとまず残置物を撤去し一時保管しつつ引き続き同意書の取得を試みるか、場合によっては訴訟を検討します。
家賃保証会社の保証が打ち切られることも
保証契約によっては入居者の逮捕等が免責事由とされている場合があります。その場合は、逮捕等の後は保証されません。そのため、契約終了手続(合意解約や契約解除手続)を急ぐ必要があります。
オーナー側としては、普段から保証契約の内容を確認しておき、入居者の逮捕等の後は速やかに動けるよう準備をしておくことが肝要です。
まとめ:3つのポイントを押さえた対応を
- 初動対応:情報源を確定し、弁護士や家族、本人と連絡を取って収容期間と意向を把握する
- 契約手続き:合意解約がベスト。難しい場合は賃料滞納を待って解除→訴訟→強制執行の流れで進める
- 残置物対策:同意書取得が鉄則。無断処分は違法行為となりリスクが大きい
どの段階でも「急がば回れ」の精神で、法的根拠に基づいた丁寧な手続きを行うことが、後々のトラブルや損失を最小限に抑える最良の方法です。

