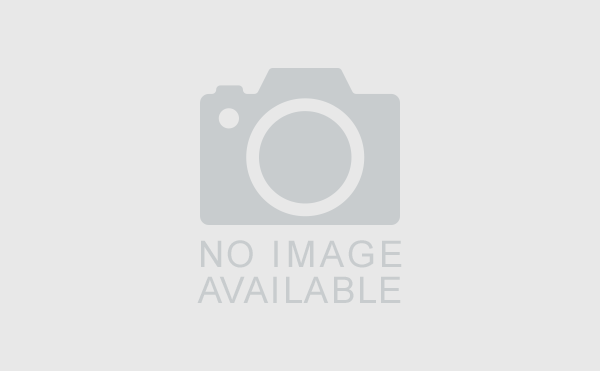市場家賃が高騰しても「家賃増額請求」は簡単ではない? 強硬策は法的リスクも
2025年6月、東京都板橋区にある築40年以上のマンションで、オーナーから入居者に対して突如、家賃を7万2500円から約2.6倍の19万円に引き上げる旨の通知がなされたという件が報道されました。
このマンションに住む50代男性の郵便受けに今年1月下旬、1枚の紙が入っていた。「家賃値上げの通知書」。現在は7万2500円の家賃を、8月分から19万円に値上げするという。約2.6倍だ。理由は「公共料金をはじめ諸物価の上昇に伴い、諸費用が増加」と記されていた。
突然、家賃2.6倍の通知 マンションのエレベーターは「使用中止」:朝日新聞(2025年6月9日付)
同時に、共用設備であるエレベーターが「使用中止」とされ、特に高齢の入居者にとって生活環境が著しく悪化。一部の入居者がやむなく退去するなど、報道でも取り上げられる騒動となりました。
その後、この件が新聞やテレビで報道された後の6月10日朝にエレベーターは使用可能となり、また、オーナーから住民に対し家賃値上げの撤回の連絡があったとのことです(「家賃倍」マンション、値上げ取り消し オーナー側「慎重に再検討」:朝日新聞(2025年6月12日付))。
この件では、高齢の入居者に対してオーナーが強硬策を取ったともとられ、またオーナーが中国の会社であったこともあって大きな議論となってしまいました。やり方を間違えると、オーナー側にも大きなリスクとなり得ますので注意が必要です。
今回は、賃料増額請求の概要とともに、強硬策を取った場合のリスクについて解説します。
目次
周辺賃料の相場が上がった場合に、オーナーは入居者に値上げを求めることができるか?
近年不動産市場は高騰しており、物件価格の相場は上昇の一途をたどっています。オーナーとしては、保有物件の賃料が周辺相場より著しく低い場合、適正化を図りたいと考えるのは自然なことです。
しかし、法律上、契約の内容を当事者が後から一方的に変えることはできないのが原則です。。
契約内容を変えるためには当事者間の合意が必要です。
この例外を定めているのが借地借家法32条であり(借地の場合は11条)、一定の場合に、当事者は賃料の増額または減額を相手に請求できるとされています。これを賃料増減額請求権といいます(以下では増額に限って説明しますが、減額の場合も内容は同じです)。
賃料増額請求について
賃料増額請求権の概要
賃料増額が請求できる要件は借地借家法32条1項に定められています。
以下の条文のとおり、その要件は、次の事情により今の賃料が「不相当となったとき」です。
- 土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により
- 土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により
- 近傍同種の建物の借賃に比較して
借地借家法32条1項
建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
手続の流れ
賃料増額請求権を行使する場合、一般的には次のような流れをたどります。
- 賃料増額通知
- 借主との協議
- 調停申立て(合意に至らない場合)
- 訴訟提起(調停が不成立となった場合)
借主との間で合意できず訴訟となる場合でも、賃料増額請求は原則として訴訟の前に調停を申し立てる必要があります。
増額が認められる場合
最初の契約をしてから、あるいは最後に賃料の合意をしてからの間(一般的にはある程度の期間が経過していることが前提とされます)に、以下のような事情により元の賃料が不当となった場合、増額が認められます。
- 周辺の類似物件の賃料と比較して、著しい乖離がある
- 固定資産税等のコストが上昇し、現在の賃料ではオーナー側の負担が過大
- 維持管理費や修繕費の高騰など、経済的合理性に基づく理由
認められたらどのくらい増額する?
増額幅については、裁判所が不動産鑑定士の意見を参考にしつつ、当該物件の特性・相場・過去の賃料水準を考慮して判断します。
とはいっても現在の相場(新規賃料)に変更されるわけではなく、現在の相場と合意時点での賃料の間に収まることがほとんどです。
そのため、急激な増額(たとえば2倍以上など)は現実的に認められにくく、段階的な増額(たとえば1.2〜1.5倍)で認められることが多いように思います。
入居者が増額に応じなかったら?
任意に応じなかったら裁判をするしかない
借主が増額に応じない場合は、調停または訴訟による解決を図る必要があります。仮に裁判で増額が認められた場合、通知を出した時点まで遡って差額分の支払いを求めることも可能です。
嫌がらせをした場合のリスク
冒頭の事案のように、オーナー側がエレベーターを止める、あるいは共用設備の利用を制限する等の圧力を加える行為は、賃貸目的物の利用を妨げる行為であるとして、債務不履行に基づく損害賠償請求の対象となる可能性があります。
また、入居者が集団で訴訟を起こしたりSNSなどネットで世に訴え出たりすることで、騒動が大きくなり対応が困難になるというリスクも考えられます。
民法611条による減額請求
また、入居者から、民法611条に基づく賃料減額の主張を受ける可能性があります。
民法611条1項では、建物の一部が使用できない場合には賃料が減額されると定められています。
民法611条1項
賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
確かに、エレベーターなど共用部分は賃貸借の目的物そのものではありませんが、この条文を類推適用することで賃料減額が認められた裁判例はあります。
したがって、エレベーターなどの共用設備を長期間停止させた場合、上記の民法611条1項類推適用や債務不履行による損害賠償請求として、オーナーが入居者から減額請求の主張を受ける可能性があります。
もっとも、類似の裁判例の傾向から、エレベーターを停めた場合に認められる家賃の減額分は、家賃の10~20%程度ではないかと考えられます。
まとめ
家賃の増額請求は、不動産オーナーにとって重要な収益確保手段の一つですが、法的な手続を踏まずに強引に進めることはリスクとなります。
ポイント整理
- 賃料増額は法的に定められた段階を踏む必要がある
- 借主との合意が得られない場合は、調停や訴訟により解決を図る
- 仮に訴訟で認められても大幅な増額は期待できない
- 圧力的手段は賃料減額や損害賠償請求の対象
- 法的な責任のほか風評リスクもある
実務における重要な視点
適切な増額を実現するには、証拠資料の整備、専門家との連携、冷静かつ段階的な対応が鍵となります。実務においては、事前の法的検討と戦略的な交渉方針の策定が、最終的な収益安定につながります。